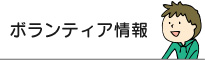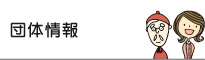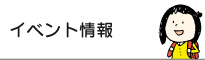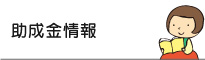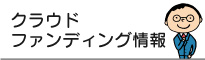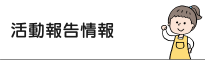■はじめに
私たちカゴメみらいやさい財団は、自助・公助だけでは解決できない社会的テーマに関して、私たちが出来ることは何かを考えてきました。
子どもの貧困による栄養バランスの悪化や、孤食による地域とのつながりの希薄化といった社会問題は、「共助の精神」なくしては解決できない問題だと考えています。
その解決のひとつである「こども食堂」は、全国におよそ10,867箇所(2025年2月)と広がりを見せています。(※)
そのなかで見えてきた課題のひとつとして、活動をしていくための「運営費の確保」が浮かび上がってきました。
私たちの2025年度助成募集に対して430団体からご応募いただき、92団体に助成を行いました。
2026年度も「今後も活動を継続していきたい」「実施回数を増やしたい」といったこども食堂に対して、最大で50万円の資金を助成いたします。
それに加えて、こども食堂を新しく始めた団体に対しても、最大10万円を助成いたします。
カゴメみらいやさい財団の理念である「子どもに笑顔を、地域に笑顔を」を一緒になって実践していただけるみなさまからのご応募をお待ちしております。
2025年12月3日(水)12:00~2026年1月16日(金)17:00
■応募先・応募方法
申請は
「むすびえ申請マイページ」からお願いします。
※「むすびえ申請マイページ」は、むすびえが運営する助成金等の申し込みサイトです。
詳しい応募方法は、動画でご確認いただけます。(説明会実施後に公開予定)
参照資料)申請者マニュアル(PDF)(システムの操作方法について)
申請設問一覧※Bコースの設問はAコースと同様のものを設定しています(Bコースでは2024度年の活動について伺う設問はありません)
(1)マイページ登録【新規のみ】
「むすびえ申請マイページ」より、マイページ登録を行ってください。
※登録済みの団体は、新たに登録する必要はありません。
マイページは、随時登録可能です。早めの登録準備をおすすめします。 登録の際、必ず口座情報を入力してください。
※団体名義の口座が開設済みであることを確認するため、団体の口座情報を伺います。
参照資料)マイページ取得の手順(PDF)
参考動画)マイページ取得の手順(YouTube)
(2)申請内容の記入
「マイページ」にログインし、募集期間中に「2026年度カゴメみらいやさい財団助成」の各コースを選択のうえ申請手続きを行います。
「申請内容」からフォームで提示される項目へご記入ください。
(3)申請書の[提出]
申請内容のフォームへ記入し、内容を確認後、「提出」ボタンをクリックしてください。
「提出」ボタンをクリックするまでは修正可能です。提出後の申請書の差し替えはできかねます。
申請についての注意事項
フォーム入力に、一定の時間が必要となります。事前に「申請設問一覧」から記入項目を確認し、記入内容をご準備のうえ、入力を開始されることを推奨します。
マイページでは、入力内容の一時保存ができます。
ただし、次の場合は適切に保存されませんのでご注意ください。
・6時間以上放置された
・同じブラウザの別タブでマイページを開いた
■助成対象事業
Aコース:こども食堂継続応援コース
助成金額:1団体につき30万円以上50万円以内
採択団体数:56団体程度
Bコース:こども食堂スタートアップ応援コース
2025年3月以降に新しく「こども食堂」を開設した事業
助成金額:1団体につき上限10万円
採択団体数:20団体程度
●カゴメみらいやさい財団のシンボルマーク(※)には、「野菜」は食を、「手」は子どもの成長を優しく見守る様子を表現しています。そのため、子どもの多様な経験や健全な成長を促す為に、農業体験や農家との連携などを歓迎し、季節野菜や地域の特産野菜など「やさい」をより身近に感じられる工夫がなされている内容であれば大変嬉しいです。
※カゴメみらいやさい財団のシンボルマークは
こちらの「助成対象事業」の右側に表示されています。
●手作り弁当配布の活動も対象としますが、一堂に介する形でのこども食堂を優先します。
●過去に当団体からの助成を受けられた団体は対象外です。また、地方自治体から運営費の助成を受けられていない団体を優先します。
●事業者からお弁当等を購入し配布する事業、フードパントリー事業は対象外です。
■助成対象期間
2026年4月1日~2027年3月31日
■助成対象団体等
a.無料もしくは低額で食事を提供する「こども食堂」の活動を行う団体(法人格の有無は問わず、宗教団体、営利団体、政治団体が運営するこども食堂は対象外とします)
b.助成金の対象となる事業を完遂する見込みがある団体
c.団体名義の口座を持っている団体
d.会計帳簿の管理ができる団体
e.「助成金受領における誓約書」を提出いただける団体
■対象経費
助成事業期間中の運営経費。ただし、他の助成金や補助金などと使途が重複していない費用に限ります。また、人件費・謝金は対象外です。
i.食材費(外注弁当購入費、フードパントリー物品購入費は対象外です)
ii.会場費
iii.交通費(ガソリン代など)
iv.消耗品費(10万円未満のもの、耐用年数1年未満のもの)
v.印刷製本費
vi.通信運搬費
vii.会議費
viii.保険料
ix.検便費
x.備品費(10万円以上のもの、または耐用年数1年以上のもの)
※最終実施報告書ご提出時に、証憑類をご提出いただきます。証憑がでない費用については助成金の充当が出来かねます。
■公募期間
2025年12月3日(水)12:00~2026年1月16日(金)17:00
詳細については
こちらをご確認ください。
■お問い合わせ先
認定NPO法人「全国こども食堂支援センター・むすびえ」内
カゴメみらいやさい財団助成事業担当(高村、合田、 常田、 藤村)
E-mail 2026kagome@musubie.org
※むすびえは、本助成事業の委託先団体になります。