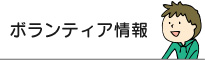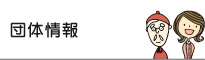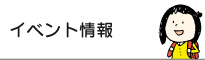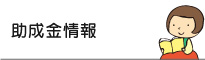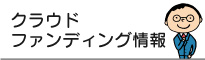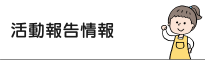くにびきエコクラブは、10月21日(金) 出雲市民会館大ホール(出雲市塩冶有原町)で開催された「第61回 島根県婦人会実践活動研究集会・環境学習の部」で、プラスチックごみ問題を扱った 当クラブオリジナル劇(脚本:山口信夫)「海亀の涙」を上演しました。劇の後には、この「プラスチックごみ問題の現状」と「どのようにしてプラごみを減らしていくのか」を映像を交えてポイント解説しました。同日、キャストとスタッフの参加者は27名。
島根県婦人会実践活動研究集会は、新型コロナウイルス感染者拡大のため、3年ぶりに約400人の会員の参加により 「 SDGs No.12(つくる責任・つかう責任」の取組 」のスローガンの下 開催されました。
「コスタリカ沖で調査をしていたテキサス大学の海洋生物学調査チームが、鼻に何かが詰まって苦しそうに呼吸する海亀を見つけた」衝撃的な映像を見た「海亀の涙」制作者(山口信夫)は 1ケ月程で脚本を仕上げ、2019年4月の初演以来今回で10回目の上演となりました。
「鼻に詰まったストローで苦しむ海亀」の映像がネットで公開(2015年8月)された後、世界中で「プラごみ削減」の流れが加速していきました。
日本でも遅ればせながら、2020年7月に「レジ袋の有料化」が、2022年4月には「プラスチック資源循環」の新しい法律がスタートしました。この法律は、プラスチックについて、単に「捨てるのを減らそう!」ではなく「捨てることを前提としない経済活動や生活習慣に改めよう!」としているのが特徴となっています。
この劇(海亀の涙)は、スーパーマーケットを経営する一家が、プラごみによる環境汚染を知り、過剰包装やレジ袋の廃止を進め、脱プラごみを目指す店に変わっていく物語。SDGs No12(つくる責任・使う責任)、No14(海の豊かさを守ろう)にも踏み込んだ内容となっています。
最後のシーンでは「竹や木を粉にして、水に溶けるレジ袋やトレイやストローを造る研究」が進むことを願う姉妹の姿を紹介しています。
(記:北垣 幸久)